FMEA(故障モード影響解析)とは?やり方・進め方と評価フォーマットの作成方法
製品や製造プロセスの品質向上を目指すにあたり、欠かせないリスク管理手法である「FMEA」。製品開発や品質管理の現場だけにとどまらず、いまではサービス業などにおいても活用される手法となりつつあります。
本記事では、FMEAの基本的な概念や評価フォーマットの作成方法のほか、FMEAを用いたリスクマネジメントの具体的な手法、さらに製品の信頼性や品質向上につながる改善策の見つけ方について考察します。
Contents [hide]
FMEA(故障モード影響解析)とは
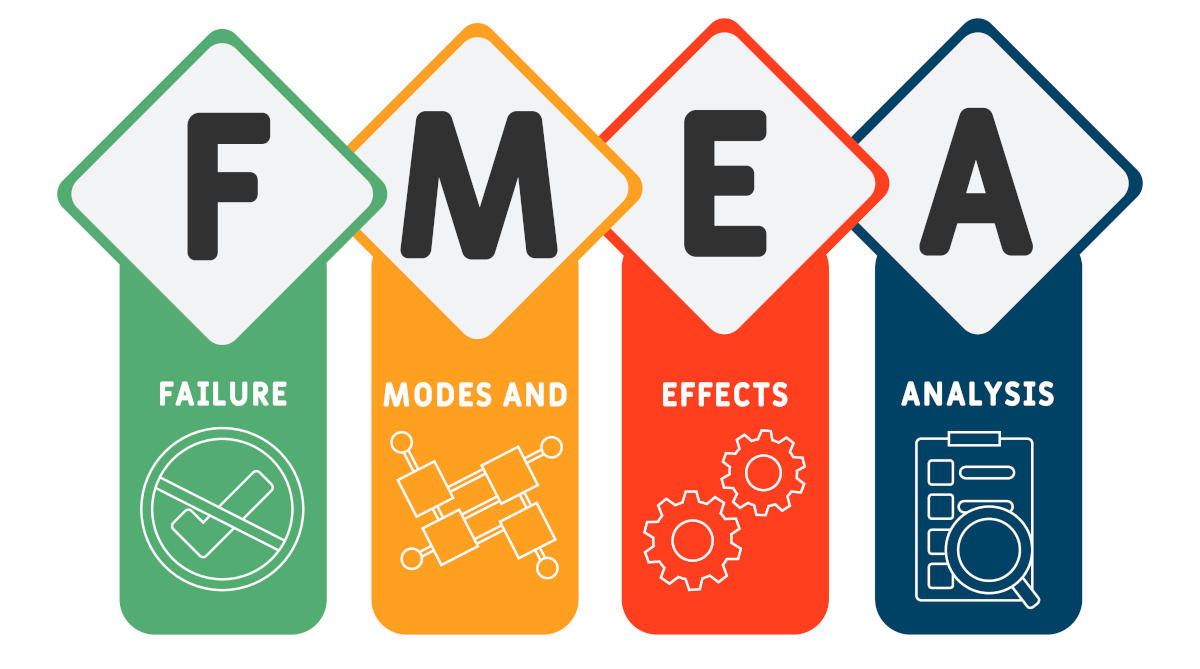
FMEA(故障モード影響解析・Failure Mode and Effects Analysis)とは、製品や製造プロセスの潜在的な故障モードを特定し、それが引き起こす影響を評価するリスク管理技術です。
● 故障モード:製品や製造プロセスが期待される機能を果たさない状態。製品や製造プロセスの欠陥あるいは機能不全を引き起こす原因となる
FMEAは、あらゆる製品やサービスの設計、製造、保守などに活用されており、自動車、航空宇宙、医療機器、電子機器をはじめとするさまざまな産業分野に取り入れられています。
FMEAの目的は、製品や製造プロセスの問題を特定して、それによって引き起こされる影響を評価し、リスクを低減することあります。将来の問題を予測し製品や製造プロセスの信頼性を向上させ、安全性を確保することができるほか、製品や製造プロセスの品質を高めることで、顧客満足度の向上にもつながります。
FMEAは、問題を「事前に」特定することができる点で非常に重要な手法です。問題の早期発見は、顧客への影響を最小限に抑えます。また、FMEAによって製品や製造プロセスの品質が高まった結果、生産性も向上するでしょう。
工程FMEAとは
工程FMEAは、製品の開発や製造工程にFMEAの手法を応用し、生産上の問題を予防するための手法です。
工程FMEAでは、工程に関わる5つの要素である、「設備」「作業者」「材料」「方法」「計測」のすべての故障モードを抽出します。製品や製造工程における重大な故障を見逃してしまうと、大きな事故につながる可能性があるため、抜け漏れのない適切な抽出が欠かせません。
また、工程FMEAは生産ラインにおける欠陥品の削減や不良品率の低減など、多くの生産上の問題を解決できるため、生産効率の向上にも役立ちます。工程の開発段階で問題を特定することで、修正コストの削減にも寄与するでしょう。
設計FMEAとは
設計FMEA は、製品の設計段階での潜在的な欠陥やリスクを特定し、修正するための手法です。設計した製品が期待通りに機能するための必要条件を特定し、その条件を満たすための設計上の要素や条件を鑑みて故障モードの影響や重要度を評価します。
設計FMEAは、開発プロセスの早期段階で欠陥を特定し、製品の信頼性や品質を向上させるために重要です。工程FMEAと組み合わせることで、製品全体の品質向上につながります。
なお製品が複雑な場合には、システム全体の機能に対するリスクを把握する機能FMEA(後述)と、各部品のリスクを把握するための詳細FMEAに分けて実施するケースもあります。
機能FMEAとは
機能FMEAは、製品やシステムの各機能について、機能不全や故障を引き起こす可能性のある原因を特定し、問題を解決するための手法です。製品やシステムの構成要素ごとに機能要件を定義し、機能の失敗モードやその原因、それによる影響を評価します。
機能FMEAは、設計EMEAの一環として実施される手法です。
FMEAとFTAの違い

FTA(故障の木解析・Fault Tree Analysis)とは、システムや製品の故障の根本原因を特定する手法です。故障モードから原因を推論し、システムの各要素間の関係を視覚的に表現することによって、システムの信頼性を評価するために使用されます。
FMEA(故障モード影響解析)とFTA(故障木解析)の違いは、その目的にあります。
● FMEAの目的:システムや製品の各要素がどのような故障を引き起こす可能性があるかを特定して、故障の重要度を評価し、リスクを低減すること
● FTAの目的:システムの可用性や信頼性を評価するために、故障モードから原因を推論し、システムの根本原因を特定すること
また、FMEAとFTは、実施方法にも違いがあります。
FMEAは、各要素の故障モードを特定し、その重要度を評価するためにリスク優先度数(RPN)を使用します。一方FTAは、システムの故障を視覚的に表現するために、イベントツリー(故障の木図)を使用します。
DRBFMとは
DRBFM(故障モードに基づく設計レビュー・Design Review Based on Failure Mode)は、トヨタ自動車が編み出した製品開発プロセスで、設計FMEAと同様に設計段階で故障モードを特定し、その対策を検討する手法です。
ただし、DRBFMは設計や工程の変更に伴って想定される不具合および回避策を把握し、設計段階でリスクを排除して不具合を未然に防ぐものです。「従来からの変更」にフォーカスを当てている点で、設計FEMAとは異なります。
FMEAの評価方法
FMEAは、「故障モードの影響度」「発生頻度」「検出難易度」をそれぞれ1~10の範囲でスコアリング評価し、これらを掛け合わせたRisk Priority Number(RPN)を算出します。
- 影響度:故障モードが発生した場合に、どの程度の影響があるかを評価する指標。スコアリング1は影響が小さく、10は重大な影響があることを示す
- 発生頻度:故障モードが発生する頻度を評価する指標。1は非常に稀であることを表し、10は頻繁に発生することを示す
- 検出難易度:故障モードを発見するために、どの程度の工数や費用が必要かを評価する指標。1は容易に発見できることを表し、10は非常に困難であることを示す
これらのスコアを掛け合わせたRPNを算出し、RPNが大きいほどその故障モードの重要度が高いことを示します。
【RPNの計算式】
RPN = 影響度 × 発生頻度 × 検出難易度
たとえば影響度が7、発生頻度が4、検出難易度が8の場合、RPNは224になります。なお、スコアリングの範囲や重要度の閾値は、企業や業界によって異なる場合があります。
FMEAのやり方・進め方
FMEAの実行プロセスを、以下の順に解説します。
- FMEAの評価フォーマットを作成する
- 工程・作業内容を記入する
- 故障モードを記入する
- 影響度、発生頻度、検出難易度を記入する
- RPNを算出する
- 対策方法を検討する
①FMEAの評価フォーマットを作成する
FMEAの評価フォーマットは、業種や企業で異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれます。
| 設計FMEAの場合 |
|
|---|---|
| 工程FMEAの場合 |
|
なお、FMEAの評価フォーマットを作成するにあたっては、いくつかの注意点があります。
まず前提となるのは、FMEAの目的を明確にすることです。目的に基づいた評価フォーマットを作成します。FMEAの評価に必要となる情報を正確に収集すること、不正確な情報を除去することも欠かせません。
また、評価基準を統一し、評価者間の評価の差異を減らすことも重要です。属人性を排除して、評価の信頼性を高められます。
具体例として、プロセスFMEAの評価フォーマットの記入例を示します。
| 工程 | 加工 |
|---|---|
| 作業内容 | 金属部品の切削加工 |
| 故障モード | 切削刃の磨耗 |
| 故障による影響 | 加工品の寸法精度低下 |
| 故障の発生原因 | 切削刃の材質不良 |
| 影響度 | 8(1-10で評価) |
| 発生頻度 | 3(1-10で評価) |
| 検出難易度 | 2(1-10で評価) |
| RPN | 48(影響度8 x 発生頻度3 x 検出難易度2) |
| 工程 | 加工 |
②工程・作業内容を記入する
続いて、FMEAの評価フォーマットにおける「工程」と「作業内容」の記入方法について説明します。
● 工程:製品やサービスを作るための一連のプロセスや手順のこと。自動車の製造プロセスであれば「溶接工程」「塗装工程」などが該当
● 作業内容:各工程において行われる具体的な作業や手順のこと。溶接工程であれば、「溶接」「部品の取り付け」などが該当
フォーマットの記入にあたっては、工程や作業内容をできるだけ詳細に記載することが求められます。評価対象となる箇所が明確でないと、評価が十分に行われないためです。
また、製品やサービスの全体像を把握し、すべての工程や作業内容を洗い出すことも重要です。評価対象が漏れていると、リスクの高い箇所が見落とされかねません。
さらに、工程や作業内容は、できるだけ具体的かつ客観的に記載することが望ましいです。主観的な表現は避け、客観的な作業やプロセスの名称を使用します。
たとえば、自動車の製造プロセスにおける「組立工程」に関するFMEAの評価フォーマットの記入例は以下のようになるでしょう。
| 工程 | 組立工程 |
|---|---|
| 作業内容 |
|
③故障モードを記入する
故障モードを抽出してフォーマットに記載する際の注意点は、「故障」や「不良」と「故障モード」を混同して抽出しないこと、そして網羅的に抽出することです。
「故障」とは、製品や工程の機能障害が、故障モードを原因として引き起こされる状態を指します。一方「不良」とは、設計通りに動作しない状態や、作業者の誤った操作により期待された機能を果たせない状態を指します。
自動車を例にすると、タイヤがパンクしている状態が「故障モード」、パンクのせいで動かない現象が「故障」です。正常に動くにもかかわらず設計通りの性能を発揮できていない場合は「不良」となります。
FMEAは、潜在的な「故障モード」を特定し、それが引き起こす影響を評価して事前に対策するための手法です。故障モードが引き起こす“現象”である「故障」や、故障モードと“無関係”の「不良」を混同して抽出してしまうと、FMEAが特定する潜在リスクへの正しい評価がなされず、正しい対策を講じられません。
また、故障モードの網羅的な抽出も必要です。
FMEAでは、解析対象の故障モードが発生した際の影響度や発生頻度、検出難易度に応じて適切な処置を行います。抽出できなかった故障モードが甚大な影響を与える可能性を踏まえると、本来必要な対策が取れなくなってしまいます。
④影響度、発生頻度、検出難易度を記入する
FMEAの評価フォーマットにおいて、影響度、発生頻度、検出難易度の評価方法は、それぞれ以下の通りです。いずれの項目においても、評価者間での一定の基準を設け、統一評価を下します。
影響度
評価対象となる部品や製造プロセスが、製品の機能や安全性に与える影響を評価します。また、製品の使用者や関係者に対して、どの程度のリスクをもたらすかを考慮します。
発生頻度
故障が発生する頻度を、数値化して評価します。評価は、製品や製造プロセスが使用される環境や条件に応じて、故障が発生する確率を考慮します。過去のデータや統計情報を参考にすることが望ましいです。
検出難易度
故障が発生した場合に、その故障をどの程度早期に発見できるかを評価します。検査の方法や頻度、機器の信頼性なども評価に加えることが望ましいです。
⑤RPNを算出する
上述のように、RPN(リスク優先度数・Risk Priority Number)は影響度・発生頻度・検出難易度の評価結果を1~10点のスケールで数値化して、各項目を掛け合わせて算出します。
RPNの値はリスクの優先度を示し、その値が高いほど対策が必要とされます。したがって、RPNの値が高い箇所について優先的に改善策を検討すべきです。RPNの値を定期的に見直し、現状の評価が妥当かどうか確認するとよいでしょう。
なお、評価対象の製品や製造プロセスが複数ある場合は、RPNの算出方法を統一し、評価基準を一定にすることが重要です。評価に用いるスケールについても、企業やチーム内で統一された基準を設けなくてはいけません。
⑥対策方法を検討する
FMEAの結果を受けて対策を講じる際には、先に述べたように、RPNが高い項目順に検討することが望ましいです。
対策と改善には、製品やサービス開発に関わるあらゆる分野からの専門知識が不可欠です。部署横断型の対策チームを編成し、多面的に解決策を検討することが望まれます。
改善策を検討した後には実際に評価実験を行い、解決策の実効性を確認します。評価実験は、可能な限り実際の状況に近い条件で行いましょう。
改善策によって問題が解決されたとしても、それを持続的に運用するためには、結果の追跡調査と継続的な施策が求められます。トレーニングプログラムやプロセス改善、規定の改定などが必要となる場合があるでしょう。
- FMEAは、製品や製造プロセスの潜在的な故障モードを特定し、それが引き起こす影響を評価するリスク管理技術
- 製品や製造プロセスの問題を特定して、それによって引き起こされる影響を評価し、リスクを低減することを目的とする
- 各要素の故障モードを特定し、その重要度を評価するためにリスク優先度数(RPN)を使用する
- RPNは「故障モードの影響度」「発生頻度」「検出難易度」をそれぞれ1~10の範囲でスコアリングし、これらを掛け合わせて算出する
- FMEAの評価フォーマットを作成するにあたり、まずはFMEAの目的を明確にすべき
- フォーマットの記入にあたっては、工程や作業内容をできるだけ詳細に記載することが求められる
- 「故障」や「不良」と「故障モード」を混同して抽出しないよう注意する
- 企業にとってFMEAは重要な品質改善ツールのひとつであり、積極的に活用していくことが求められる


