派遣社員も福利厚生の対象になる?派遣元・派遣先での適用条件や待遇格差を考える
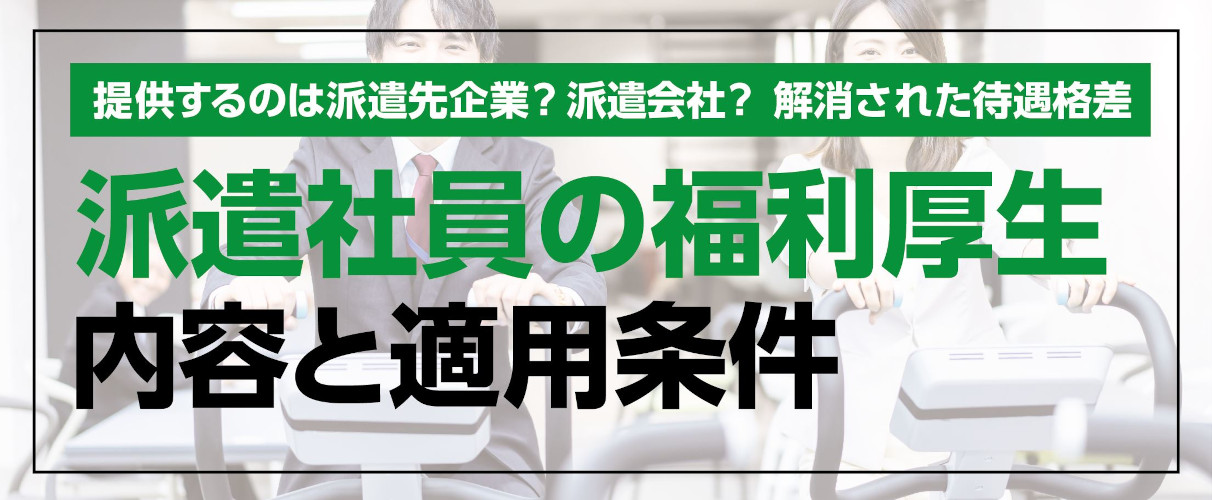
「派遣社員は福利厚生制度の対象外」「正社員よりも待遇面で劣る」。派遣社員など非正規雇用で働くにあたり、このような懸念があるかもしれません。
しかし、労働者派遣法の改正により、非正規雇用労働者の待遇は整備され、派遣社員であっても正社員と同等の福利厚生を利用できるようになっています。
本記事では、派遣社員の福利厚生に関連するルールや利用可能な福利厚生制度について解説します。
Contents
派遣社員も福利厚生の対象になる

前提として、福利厚生制度は雇用の形態を問わず受けられるものです。したがって、派遣社員であっても福利厚生の対象となります。
なお、福利厚生制度は以下の2種類に大別されます。
- 法律で定められている「法定福利厚生」
- 企業が独自に提供する「法定外福利厚生」
このうち、後者の法定外福利厚生は、かつては派遣社員に対しては「配慮義務」に留められていました。たとえば企業が独自に定める特別休暇などの福利厚生の対象を正社員のみに限定していても、罰則などはありません。こうして生じた正社員との待遇格差から、「派遣社員は福利厚生制度を受けられない」のイメージが広まったとみられます。
そこで2020年、労働者派遣法の改正により、同一労働同一賃金の施行が示されました。これは政府が推進する働き方改革とも関連する施策で、正社員と派遣社員の間に存在した不合理な待遇差の是正が企業に求められるようになったのです。
これにより、派遣社員であっても正社員と同等の福利厚生を受けられるようになりました。
ただし、これまでも健康保険や厚生年金保険など「法定福利厚生」に関しては、非正規雇用の労働者に対しても提供されていました。法改正を経て利用拡大が推進されたのは、「法定外福利厚生」です。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは、雇用形態を問わず同じ仕事に従事する労働者には同一の賃金を支払うという概念です。
狭義には、「基本給や昇給・ボーナス・各種手当において、雇用形態などに起因する不合理な待遇差はあってはならない」という考え方ですが、2020年の法改正を経て、賃金のみならず福利厚生やキャリア形成・能力開発支援等も含めた「待遇全体」での格差解消が企業に求められています。
待遇差改善を図る具体的な方法として、派遣元企業は「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを採用し、派遣社員の待遇を定めることになっています。
派遣先均等・均衡方式の場合
派遣先均等・均衡方式とは、派遣社員の待遇を派遣先企業の正社員と同等のものとする方式です。派遣社員は賃金のみならず、福利厚生も含めて派遣先企業の正社員と同等の待遇を受けられます。
たとえば派遣先企業が特別休暇制度や食事補助制度などの法定外福利厚生を独自に運用している場合、派遣社員も制度の対象となるということです。
ただし、派遣先均等・均衡方式を採用する派遣会社から派遣社員を受け入れる企業は、派遣社員を受け入れる前に、正社員の待遇情報を派遣会社に提供する必要があります。同方式を採用している派遣会社は全体の約1割に留まっており、後述の労使協定方式を採用している企業が大半です。
労使協定方式の場合
労使協定方式とは、派遣会社と労働者の代表が労使協定を締結し、派遣社員の待遇を決定する方式です。
この場合、派遣社員の賃金については、厚生労働省が公表する「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を満たすことが求められます。つまり派遣先の賃金ではなく、一般的な基準に合わせて決まるということです。
福利厚生においては、法定・法定外ともに派遣元企業の制度を、派遣元企業の正社員と同様に利用することが原則となります。労使協定方式の場合、法定外福利厚生の内容は派遣元企業の制度に準拠するため、派遣先企業が独自の福利厚生制度を運用していても、派遣社員は同様の法定外福利厚生を受けられないことがあります。
ただし、給食施設・休憩室・更衣室といった施設の利用や、職務に必要な教育訓練については、派遣先企業の正社員と同等の待遇を派遣先企業から受けられます。
派遣社員にも適用される法定福利厚生【派遣元企業から】
先述のとおり、福利厚生には法律で定められた「法定福利厚生」と、企業が独自に実施する「法定外福利厚生」があります。
法定福利厚生はその名のとおり、法律で具体的な内容が決まっているため、基本的にはどの企業であっても同じです。
| 法定福利厚生の項目 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険 |
|
| 厚生年金保険 |
|
| 雇用保険 |
|
| 労災保険 |
|
| 年次有給休暇 |
|
| 産前休業 |
|
| 産後休業 |
|
| 育児休業 |
|
| 子の看護休暇 |
|
| 介護休暇 |
|
| 介護休業 |
|
| 育児・介護のための短時間勤務 |
|
| 健康診断 |
|
これらの法定福利厚生には、それぞれ加入や付与要件が定められていますが、雇用形態は要件に含まれません。正社員・派遣社員の区別を問わず、要件に該当していれば利用できます。
法定外福利厚生は適用される?【派遣元・派遣先企業から】
法定外福利厚生は、企業が独自に運用する福利厚生です。
派遣社員の場合はやや複雑で、基本的には法定外福利厚生も派遣元企業の制度を利用する方式となりますが、一部の制度においては派遣先企業の制度を利用します。
法定外福利厚生の具体的な内容や充実度は、企業によって異なりますが、代表的な項目には以下のようなものがあります。
| 法定外福利厚生の項目 | 内容 |
|---|---|
| 各種手当等 | 通勤手当・資格手当・賞与・退職金など |
| 住宅支援 | 家賃補助・社宅・社員寮など |
| 慶弔金・見舞金 | 結婚祝い金・出産祝い金・災害見舞金など |
| 特別休暇 | リフレッシュ休暇・バースデー休暇など |
| 教育訓練・能力開発 ※派遣先企業が実施をする必要があるもの |
業務に必要な能力の獲得のために実施するもの |
| 自己啓発 | 自己啓発のために受講する研修やセミナーに関する機会提供や費用負担など |
| 福利厚生施設 ※派遣先企業が利用を認める義務がある施設 |
派遣先企業のオフィス等に設置されている給食施設・休憩室・更衣室の利用 |
| 福利厚生施設 ※派遣先が利用の配慮をする義務がある施設 |
派遣先企業のオフィス等に設置されている物品販売所・病院・浴場・理容室・保育所・図書館・講堂・娯楽室・運動場・体育館・保養施設などの利用 |
これらの法定外福利厚生は、派遣先均等・均衡方式の場合は派遣先企業の内容に、労使協定方式の場合は派遣元企業の内容に準じます。
先述のとおり、派遣会社の多くは労使協定方式を採用しており、法定外福利厚生の内容は派遣会社のものと同等になっているケースが主流です。
ただし、業務に必要な能力のための教育訓練・能力開発や、教職施設・休憩室・更衣室については、派遣社員も派遣先企業の福利厚生を利用できます。
派遣社員の福利厚生はいつから適用される?
法定福利厚生については、勤続年数などが適用要件とされるものがいくつかあります。
| 福利厚生の項目 | 利用開始日 |
|---|---|
| 健康保険 | 入社日から利用可能 |
| 雇用保険の失業保険 | 受給には離職日以前の2年間で被保険者期間が通算して満12ヶ月の勤務が必要 |
| 労災保険 | 入社日から利用可能。初出勤当日の労災の怪我などでも受給可能。ただし、休業初日から3日目までは労災保険ではなく派遣元企業が休業補償を行う |
| 年次有給休暇 | 入社から最短で6か月経過で発生。付与日数は勤務年数と1年間の所定労働日数により変動 |
| 産前休業・産後休業・育児休業 | 勤続年数に関係なく利用可能。ただし、産前休業・産後休業については期間開始日に雇用契約中であること、育児休業については子どもが1歳6か月になる日までに雇用契約が満了することが明らかでないことが要件 |
| 子の看護休暇・介護休暇 | 原則、勤続年数に関係なく利用可能だが、労使協定により雇用期間が6か月に満たない場合や週の所定労働日数が2日以下の場合は取得できないことがある |
| 介護休業 | 原則、勤続年数に関係なく利用可能だが、労使協定により雇用期間が1年に満たないなどの場合は取得できないことがある。また有期雇用契約場合、同一の事業主に雇用された期間が1年以上であることなどの要件がある |
| 育児・介護のための短時間勤務 | 原則、勤続年数に関係なく利用可能だが、労使協定により雇用期間が1年に満たない場合や週の所定労働日数が2日以下の場合は取得できないことがある |
| 健康診断 | 健康診断をいつ受診できるかは派遣会社との契約による |
一方、法定外福利厚生に関しては、企業が独自に具体的な内容や利用要件を定めており、いつから適用されるかは個々の制度に準拠します。
福利厚生における待遇格差で違法となるケース

ここまでの内容を踏まえ、労働者派遣法上における「派遣社員と正社員の不合理な待遇差」と判断される可能性があるケースを考察します。
派遣先の社員食堂の利用を断られた場合
派遣先企業のオフィスにある社員食堂を利用しようとしたところ、「ここは正社員の福利厚生として運営されている」「派遣社員は使えない」と断られてしまった場合です。
これは不合理な待遇差とみなされる可能性が高いです。給食施設や休憩室、更衣室といった施設においては、派遣社員にも利用を認める「義務」が派遣先企業に課されています。
業務に必要な研修等で正社員にはない実費負担を求められた場合
派遣先企業の上長などから指示を受け研修を受講したところ、「正社員の受講料は会社が負担するが、派遣社員の受講料は実費負担してもらう」と通告される場合です。
こちらも不合理な待遇差とみなされる可能性が高いです。業務に必要な能力のために実施する教育訓練・能力開発は、派遣先企業がその機会を提供する義務があります。したがって、正社員との間に不合理な差を設けてはならないと考えられます。
育休や短時間勤務の申出を派遣社員であるからと断られた場合
育児のために、育児休暇や短時間勤務を申し出たところ「派遣社員には認めていない」と断られてしまったケースです。
こちらも不合理な待遇差とみなされる可能性が高いです。育児休暇や短時間勤務は一切の雇用形態を問わず、すべての労働者が対象の法定福利厚生であるためです。
ただし、法定福利厚生については派遣先企業ではなく、派遣元企業の福利厚生を利用します。そのため、育休や短時間勤務の際の手当てや賃金については、派遣会社に申し出ます。
- 派遣社員であっても、正社員と同等の福利厚生を利用できると法律によって定められている
- 健康保険や厚生年金保険など「法定福利厚生」は、派遣会社が提供の義務を負う
- 企業が独自に運用する福利厚生制度である「法定外福利厚生」を派遣社員が利用する場合は、基本的には派遣会社の制度を利用する方式となるが、教育訓練や施設利用など一部の制度においては派遣先企業の制度を利用する


