派遣の3年ルールとは?目的や適用外となるケース・無期雇用に延長する方法を解説
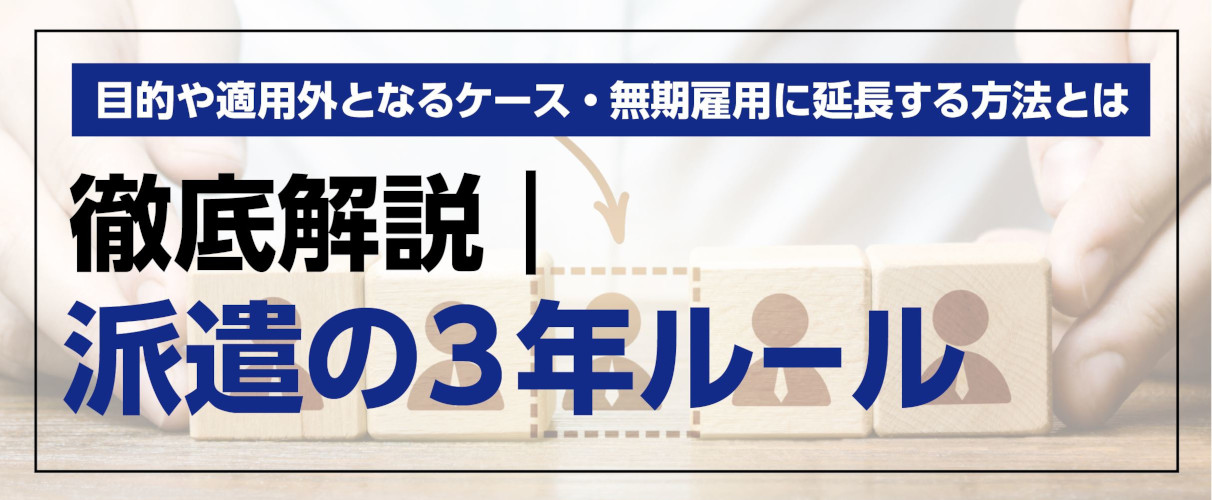
2015年の労働者派遣法改正により、派遣会社(派遣元企業)、派遣先企業、派遣労働者には「派遣の3年ルール」が適用されることとなりました。この派遣の3年ルールとは、有期雇用派遣社員が同一の職場や部署での労働期間を原則として最長3年までとするルールのことです。
この3年ルールによって、「3年経過後に就労先がなくなってしまう」と不安を抱えている派遣労働者も少なくないはずです。ルールに関する正しい知識を頭に入れておきましょう。
また、派遣会社や派遣先企業も、法令遵守のためにも労働者派遣法における通称「3年ルール」について、制定された目的やルールの内容をあらためて把握し、適切な雇用を実現させましょう。
Contents
派遣の3年ルールとは?
派遣の3年ルールとは、「有期雇用派遣社員が同一の職場あるいは部署にて継続して働ける期間が最長3年まで」と定められた労働者派遣法におけるルールのことです。
第三十五条の三 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
第四十条の三 派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。
引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)|e-GOV法令検索派遣の3年ルールは、2015年の労働者派遣法の改正によって定められたものです。本ルールは、2015年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者に適用されます。
派遣先の 「事業所単位」 の期間制限
派遣の3年ルールは、「事業所単位」かつ「個人単位」の期間制限が設けられています。
事業所単位の期間制限とは、「同一の事業所において3年の派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れることはできない」というルールです。厚生労働省が派遣先企業に向け公開している資料「派遣先の皆様へ」からの引用を交え、派遣先の事業所単位の期間制限についてのルールを説明します。

画像引用元:派遣先の皆様へ|厚生労働省
なお、事業所単位の考え方は、基本的に雇用保険の適用事業所と同様です。工場、事務所、店舗などが場所的に独立している、あるいは経営単位として人事や経理などがある程度独立している、施設として一定期間継続するものなどが該当します。
派遣先の 「個人単位」 の期間制限
「個人単位」の期間制限では、「事業所単位」の期間制限を延長した場合であっても、課などの組織単位で3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることができないと定められています。
組織単位とは、いわゆる課やグループを指します。業務としての類似性や関連性が認められる場合や、組織の長が業務分配、労務管理上の指揮監督権限を有するものは同一組織とみなされ、3年を超えて派遣を延長することはできません。

画像引用元:派遣先の皆様へ|厚生労働省
派遣の3年ルールの目的
派遣の3年ルールが設けられた背景には、派遣社員の雇用の安定化があります。政府は、継続して働く派遣社員の正社員化や無期雇用派遣への転換を促すために、同ルールを制定しました。
つまり、派遣の3年ルールの適用によって、派遣社員は3年間同じ企業で働くことで、派遣先企業から直接雇用される可能性が生まれます。その一方で、3年以内に契約を解除され、新たな就業先を探さなければならないこともあります。
派遣先企業の側から見ると、優秀な派遣労働者を長期間雇用できなくなる可能性が生じるため、派遣労働者を正社員などとして受け入れる必要が出てきます。
派遣会社は3年ルールを正しく理解して、派遣労働者の派遣期間を適性に管理し、法令遵守を徹底しなければいけません。
派遣の3年ルールのメリットとデメリット
上述した派遣の3年ルールが設けられた背景を踏まえると、派遣労働者、派遣先企業、派遣会社それぞれのメリット・デメリットが浮かび上がります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 派遣労働者 |
|
|
| 派遣先企業 |
|
|
| 派遣会社 |
|
|
派遣の3年ルールが適用外となるケース

派遣の3年ルールには、いくつかの例外があります。以下のいずれかに該当する場合、3年以上継続しての雇用が可能です。
- 無期雇用派遣
- 期間の定めがあるプロジェクトに関わっている
- 勤務日数・時間が通常の半分以下
- 休業中の社員の業務を代替している
- 60歳以上
無期雇用派遣
無期雇用派遣とは、派遣元企業と派遣労働者の間で契約終了の期間を決めずに雇用契約を交わす制度です。無期雇用派遣の労働者は3年ルールの適用外となり、派遣先企業は3年以上継続しての雇用が可能です。
無期雇用派遣について、詳しくはこちらの記事をご覧下さい
期間の定めがあるプロジェクトに関わっている
期間の定めがあるプロジェクトに関わる派遣社員は、そのプロジェクトが終了するまで3年を超えて雇用を継続できます。これは、終期がすでに決まっているプロジェクトに関連する業務であれば、常用代替のおそれがないことから3年ルールの適用外とされました。
ただし、3年ルールの適用外となるプロジェクトの業務は、事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務とされており、かつ一定期間内に完了する必要があります。
勤務日数・時間が通常の半分以下
派遣労働者の1ヶ月当たりの勤務日数・時間が、派遣先に雇用されている通常の労働者の半分以下、あるいは10日以下である場合には3年ルールの適用外となります。
休業中の社員の業務を代替している
産前産後休業や育児休業、介護休業を取得中の社員に代わり、その社員と同じ業務を行う派遣労働者は、休業中の社員の代理としての契約となること、かつ契約期間が明確であるため3年ルールの適用外です。
60歳以上
60歳以上の派遣労働者も、3年ルールの適用外です。この背景には、高齢者の就労先の確保が困難であることが挙げられます。
なお、派遣就業開始年齢が60歳以下の場合でも、3年経過後に60歳以上となっている場合は、3年ルールの適用外となります。
5年ルールとの違い
5年ルールとは、有期労働契約が繰り返され、通算5年を超える場合には労働者からの申し込みによって無期労働契約に転換できる制度のことです。
この制度は、派遣の3年ルールとは異なり、派遣労働者を含むすべての有期雇用契約の労働者が対象です。
3年経過後も辞めたくない場合

派遣就労から3年経過後も、派遣先企業での業務を辞めたくない、続けたい場合は、以下の方法で労働期間の延長が可能です。
- 無期雇用派遣に変更する
- 部署異動する
- 派遣先と直接雇用を結ぶ
無期雇用派遣に変更する
就業から5年以上が経過した派遣労働者は、前述の「5年ルール」によって、派遣会社にて無期雇用派遣に変更してもらうことが可能です。無期雇用派遣への転換によって、期間に限りなく同一の企業にて派遣労働者として受け入れてもらえるようになります。
ただし、無期雇用派遣は派遣先企業との直接雇用ではありません。派遣会社と派遣先企業の契約の終了により、就業先を失ってしまう可能性があります。
部署異動する
「派遣先の 『個人単位』 の期間制限」の項にて説明したとおり、派遣労働者は同じ組織で3年以上働き続けることはできません。ただし、部署を異動することでさらに3年間同じ企業で働くことができます。
なお、部署異動後は新たに3年ルールが適用されることになる点に注意してください。
派遣先と直接雇用を結ぶ
派遣から3年後には、派遣先企業に正社員登用されるなど、直接雇用を結ぶことも可能です。直接雇用に切り替わることで、派遣労働者は派遣会社ではなく派遣先企業に雇用されることとなります。
これにより、派遣先企業の他の一般社員と同様の働き方が実現します。
- 派遣の3年ルールとは、「有期雇用派遣社員が同一の職場あるいは部署にて継続して働ける期間が最長3年まで」と定められた労働者派遣法におけるルールのこと
- 「事業所単位」かつ「個人単位」の期間制限が設けられている
- 「事業所単位」の期間制限とは、同一の事業所において3年の派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れることはできないというルール
- 「個人単位」の期間制限とは、課などの組織単位で3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることができないというルール
- 継続して働く派遣社員の正社員化や無期雇用派遣への転換を促すために、派遣の3年ルールが制定された
- 派遣期間3年を超えたあと、派遣先企業から正社員登用されたり、派遣会社から無期雇用として契約を締結してもらえたりする可能性もある
- 無期雇用派遣や休業中の社員の業務を代替している場合などは、派遣の3年ルールの適用外となる


